オクラ カメムシ類
>> ホーム >> ピーマン・ししとう モザイク病(BBWV) >> メロン チビクロバネキノコバエ >> オクラ カメムシ類
病害虫情報 : 2012/10/17
高知県 病害虫・生理障害台帳

果実を吸汁するミナミアオカメムシ成虫

ブチヒゲカメムシ成虫

幼果を吸汁中のブチヒゲカメムシ幼虫
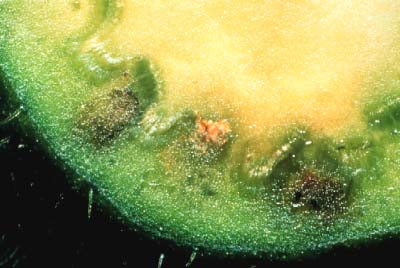
吸汁部位の切断面;スポンジ状になる。
作物名
オクラ
一般名称
カメムシ類(オクラ)
学術名称
Nezara viridura (Linnaeus)、
Dolycoris baccarum (Linnaeus)
症状
オクラにはミナミアオカメムシ、ブチヒゲカメムシなどが発生する。
成、幼虫が朔果や蕾を吸汁加害する。外見上、被害はほとんどわからないが、朔果を切断すると子実が変色したり、吸汁部が褐色に変色している。朔果の基部が加害されると内部がスポンジ状になる。
発生条件
ミナミアオカメムシはシュロやキミガヨランで成虫態で越冬する。越冬成虫は4月頃から活動を開始し、ばれいしょやイタリアンライグラス、ムギ及びイネ科雑草などで世代を経過する。幼虫は5齢を経過し、1カ月程度で成虫となる。年間に4~5世代経過する。
ブチヒゲカメムシは成虫で越冬し、越冬後はきく科やまめ科植物に移り繁殖する。これらの個体がオクラに飛来してくる。
両種ともにオクラでは8月中旬以降に発生が多くなってくる。
対策
アブラムシ類の防除を行うことで、本種の抑制も可能な場合がある。
ツイート
