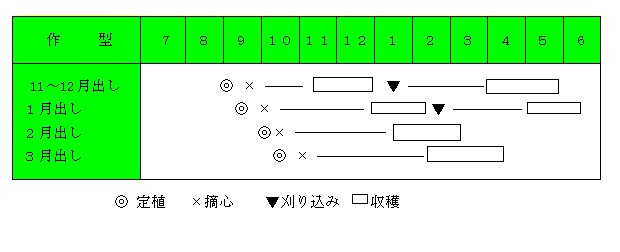2)作型(シュッコンカスミソウ)
>> ホーム >> 2)作型(シュッコンカスミソウ)
品種登録の関係で自家増殖できない品種が増加しており、また、自家増殖可能なブリストルフェアリーも購入苗による生産が大部分になっているため、苗を自家生産することは少なくなっている。
しかし、ブリストルフェアリーについては、安定生産と作型に応じた系統の利用という点から、産地での系統選抜と苗の自家生産が望まれる。10~12月出し用の挿し芽時期は高温期のために挿し芽中に挿し穂が腐敗しやすいが、1月出し以降に利用する苗は自家生産したい。
ア.親株管理
- a.系統選抜
ブリストルフェアリーには、早晩生等で多くの系統がある。系統選抜は、10月中旬~11月定植で無電照、無加温条件(ロゼット化しやすい条件下)で栽培したほ場で行い、ロゼット化せず、仕立てた芽が揃っており、しかも切り花品質の優れた株を早晩生毎に選ぶ。
- b.親株の養成
親株は、本圃に定植する株数の1割程度用意する。春に採花後、刈り込んで若返りを図った株から採った穂を親株とする。親株は、地床あるいは木箱に植えるが、地床よりも底の深い木箱に植えた方が水管理が容易で節間の詰まった硬い良い穂が取れる。軟弱な穂は水分が多いため、挿し芽床(特にミスト利用の場合)で腐敗しやすい。
親株とする挿し芽苗を定植して活着後、新芽が伸長してきたら、4節ほど残して生長点が残らないように展開中の葉を重ねて引き抜くように摘む(ソフトピンチ)。その後10~15日して腋芽が展開葉4枚、未展開葉2枚となった時点で1~2節残してソフトピンチし、500倍程度の液肥を施用する。これを繰り返して、3~4回目のピンチで採ったものを挿し穂とする。1株から20~30本採穂できる。一度に挿し芽する場合は、早く採った挿し穂をポリ袋にいれて2~3℃で冷蔵すると3週間程度の貯蔵が可能である。なお、4~5回程度採穂すると、株が老化し貧弱な穂となるので、順次更新する。また、節間伸長している穂や葉の細い穂は早期抽台して貧弱な切り花しか採花できないので除く。
地床での親株養成
元肥としてN成分で1kg/a程度施用したほ場に20cm×20cmの2条植えか3条植えで定植し、採穂の一週間前には灌水を止める。
木箱での親株養成
幅45cm×長さ55cm×深さ15cmの木箱に15cm×10cm程度(15株/箱)で定植する。
イ.育苗
- a.挿し芽
挿し芽は、5月までは10℃程度に加温したハウス内のトンネル密閉挿しで行い、気温が高い6月以降はミスト装置下で挿し芽する。パーライト2号(ネニサンソ)を水に浮かせて、浮いたもののみをトロ箱か深目の育苗箱に詰めて挿し床とする。挿し穂は、展開葉1対に調整して1時間程度水揚げした後、挿し穂の基部にオキシベロン粉剤を粉衣するかオキシベロン液剤の5倍液に30~60秒間基部を浸し、2~3cm間隔に挿す。一度萎れると水揚げが非常に悪くなって発根が悪くなるため、採穂から挿し芽まで絶対に萎れさせないようにする。
(左)挿し芽作業 (右)発根したところ
挿し芽から11~15日後には発根が始まるので、発根を確認後に1000倍の液肥を施用し、挿し芽の14~18日後にはミスト外に搬出して同様の液肥を施用し、順化する。
密閉挿し
挿し床は最低夜温を10~15℃としたハウス内に置き、ポリエチレンかビニルフィルムでトンネルする。挿し芽直後には細かいジョロで十分に灌水し、ダイオネット(90%遮光)+寒冷紗(50%遮光)で被覆する。その後、挿し芽2~3日後の夕方にダイオネットを除いて寒冷紗のみとする。挿し芽後、発根までは床土が乾かないように葉水程度に灌水する。
ミスト施設による挿し芽
ミスト施設に搬入後、3日間は2重に寒冷紗で遮光して萎れさせないようにする。その後は寒冷紗を1枚とすると概ね11日後には発根を始める。
ミスト施設での挿し芽
- b.鉢上げ
挿し木床の裏から根が少し出る状態となれば、ポット(2.5号か3号)に日陰で鉢上げする。セル成型苗を購入して鉢上げする場合には、苗が到着後すぐに鉢上げできるように準備しておく。鉢土には、土と完熟堆肥を1:1~2で混合したものにpH6.5、EC0.8~1.0になるよう施肥したものを用い、必ず土壌消毒しておく。なお、鉢上げ後の枯死原因には
- 硬化処理の失敗
- 老化苗を植えた場合
- 鉢土に原因がある場合
等が考えられる。
8月下旬~9月10日までに定植する作型では、定植日が3日遅れると収穫が1~2週間遅れ、9月下旬以降に定植する作型では定植日が1~2週間ずれても収穫期には大差がない。
ツイート