家庭菜園(ハクサイ)
>> ホーム >> 家庭菜園(ハクサイ)
1.作り方のポイント
- 昨型にあった品種を選び、適期に種まきをします。遅れたり、早すぎて、低温期に種まきをすると結球しなかったり、トウ立ちが早くなります。
- 連作をを避けます。アブラナ科野菜(ダイコン、カブ、キャベツ類)と連作すると根コブ病など土壌苗お害が増えるので、他の野菜と輪作します。
- 土を深く耕します。根を深く張らすと充実した大玉になります。
- 石灰不足による心葉の縁腐れ、ホウ素欠乏による心葉のろくの亀裂などが生じやすい時は、元肥施用時に補っておきます。
- チッソを多く施しすぎると、“ゴマ症”の原因となりますので注意します。
2.年間の作付け計画
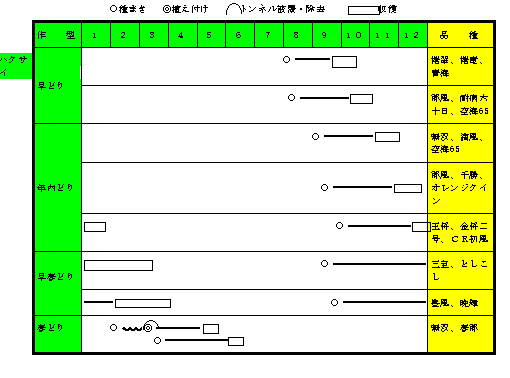
3.作型と品種
1)早どり
9~10月上旬どり作型には、耐暑性が強く、高温結球性の優れており、 種まき後40~55日で収穫できる品種が最適です。上記の品種は、外葉に毛がないので、ヌキ菜や半結球ハクサイとしても利用できます。
2)年内どり
この作型は比較的栽培の容易な時期です。なお、上記のオレンジクインは、従来のハクサイと異なり、球のなお部がオレンジ色でサラダ料理にも利用できます。
3)早春どり
9月に種をまき、1~3月に収穫する作型では、生育後半が低温・乾燥期にあたるため、耐寒性と低温結球性に優れており、種まき後100日前後で収穫できる品種が適しています。なお、この作型では、年末から年明けにかけて球頭部をワラなどで結束することが大切です。
4)春どり
5月どりのトンネル栽培は、必ず暖かいハウスなどで育苗する必用があります。そしてトンネルの換気操作で失敗し、葉焼け等を起こす例もありますので、温度管理に注意して下さい。
4.畑の準備
ハクサイの根は、広くしかも深く伸びるので、耕す深さは20cm以上にできれば理想的です。
施肥は元肥主体とし、1平方メートル当たり苦土石灰100~150g、有機入り化成肥料 150~200g、FTE3gを全面施用してからうね立てをします(FTEは有機化成肥料と混合した方が施肥しやすい)。
うね幅は60~70cmとし、排水が悪ければ高うねとします。
5.種まき
40cm間隔で1カ所4~5粒をまき、種が隠れる程度に薄く覆土し、乾燥防止に新聞紙をかぶせて上から十分灌水します(発芽したら、新聞紙は夕方に除く)。
6.間引き
1回目は本葉2~3枚目の時に2~3本にし、2回目に本葉7~8枚の時、1本にします。
7.追肥
1回目は、本葉6~7枚時に1平方メートル当たり燐硝安加里S226で30~40gをうね肩に施し、中耕、土寄せします。第2回目の追肥は、結球にいる前に行います。追肥が遅れると作業時に外葉を痛めたり、球の肥大が鈍くなり結球が不十分となります。
8.収穫
品種によって収穫までの期間が違うが、およそ種まき60~100日です。結球したハクサイの頭を押さえてみて、堅くしまっているようなら収穫できます。
早生ハクサイは、結球がすすんだらできるだけ早く収穫します。遅れると軟腐病の発生が多くなるので、遅れないように収穫します。中晩生ハクサイは、よく結球して堅くしまった頃に収穫します。
ツイート
