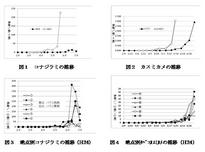グリーンフォーカス 平成25年7月号
>> ホーム >> グリーンフォーカス 平成25年7月号
トマトにおける土着天敵利用技術の検討
1.背景・目的
施設トマト栽培では、タバココナジラミが媒介するウイルス病(黄化葉巻病)が問題になっていて、生産者は対応に苦慮しています。このウイルス病にかかるとその株からの収穫ができなくなるだけでなく、そのウイルス感染株を吸汁したコナジラミは新たにウイルスを獲得し、生存中は他の株にウイルスを伝染し続けます。トマト栽培では、化学農薬の効きにくいコナジラミが増えてきていて、防除が困難になりつつあります。
そこで、化学農薬のみに頼らない害虫防除対策として、土着天敵であるタバコカスミカメの利用を検討しました。
2.実証内容
1)天敵放飼時の害虫発生状況および天敵の導入方法
コナジラミがほとんど見えない状況で、平成24年3月5日に9aのハウスにタバコカスミカメ1000頭を導入しました。
比較対照として、前年の平成23年3月8日および22日に、隣接ハウス(15a)において、コナジラミが発生している状態で、10a当たり合計500~1000頭を導入しました。
2)バンカープランツの設置
天敵が定着しやすいように、平成24年はハウス東部分にバンカー植物としてクレオメおよびゴマを設置しました。
なお、平成23年には設置していません。
3)調査方法
調査の間隔は約10日としました。ハウス内の6カ所において、トマト各10株の上位葉および下位葉各1葉に寄生するコナジラミ数およびタバコカスミカメ数を数えました。

3.結果の概要
平成23年には5月からコナジラミが急増していましたが、平成24年は栽培終了まで低い密度で推移しました(図1)。一方、タバコカスミカメは、平成23年は4月から増え始めたのに対して、平成24年は初期から低密度で推移していて、栽培期間の終盤である6月から急激に増えました(図2)。平成24年は天敵が害虫の増殖を長期間にわたって抑制しており、今回は黄化葉巻病の発生も見られませんでした。今回の実証試験では、コナジラミ以外にトマトサビダニが発生しており、そのために天敵に影響の少ない薬剤防除を1回行いました。
6カ所の調査地点ごとに、コナジラミの発生状況にばらつきがありました。クレオメやゴマのバンカープランツを設置しているハウスの東部分では、コナジラミの発生は少ない傾向でした。一方、設置していない西部分ではコナジラミが6月に一時的に急増し、その後タバコカスミカメが増殖するにつれて、コナジラミの発生が少なくなっていくという状況でした(図3、4)。
以上のことから、タバコカスミカメはコナジラミ防除に有効であると思われました。
なお、防除効果を早くから安定させるためには、コナジラミなどの害虫がほとんどいない状況から天敵を放飼することと、クレオメやゴマなどのバンカー植物をまんべんなく設置することが適当と考えられました。
今後の課題
天敵を利用していくと殺虫剤の散布回数が減るため、これまで問題になっていなかった害虫が発生する可能性があります。また、トマトで使用している天敵に対して影響の少ない薬剤が農薬登録されていない状況ですので、今後対策を検討していく必要があります。
また、天敵の利用が利用が進むと、殺菌剤の散布回数も減る可能性がありますので、病害対策も徹底していく必要があります。
ツイート