家庭菜園(ソラマメ)
>> ホーム >> 家庭菜園(リュウキュウ) >> 家庭菜園(ソラマメ)
1.作り方のポイント
- 連作障害が出やすい作物なので、連作を避けましょう。3~4年は休みたいものです。
- 耕土の深い地力のあるところに適します。
- 土の酸性に弱いので、石灰を施すことを忘れてはいけない。また、土の乾燥にも弱い。
- チッソ分が多いと根粒菌の働きが悪くなるので、施肥量は1平方メートル当たり10g以下とします。
2.年間の作付け計画
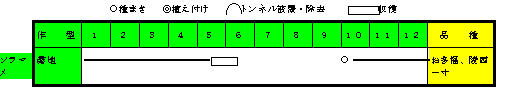
3.畑の準備
排水不良地ではうねを高くします。苦土石灰はうねを作る前に必ず施します。うね幅は普通畑で1.1~1.2mとし、1条まきとします。乾田では、うね幅1.8mのやや低いうねとし、2条まきます。
施肥例:苦土石灰150~200g、燐硝安加里S604 50g、ヨウリン30g
4.種まき
1平方メートル当たりの種子量は、陵西一寸で約10ml(7g)で、株間50cmの1条種きとします。オハグロ部分(発芽部)をななめ下または横にして、種子が隠れる程度に覆土します。
5.整枝
放任でも良いが、各枝が1~2節開花した頃、徒長した枝や幼少の枝を分岐点から切り取り、太い枝を5~6本残すことにより大サヤ率が増加します。
6.土寄せ
倒伏を防ぐために、除草中耕を兼ねて3月中、下旬の整枝後すぐに株元に、5~6cmの厚さに土寄せし、株内を広げます。土入れは倒伏防止だけでなく、除けつ、除草にも役立ちます。
7.倒伏防止
図のように倒伏防止のため、支柱(1m前後)を2~3m間隔に立ててテープあるいはネットを張って倒れないようにすると良い品質のサヤがとれます。
8.追肥
11月中~下旬と2月上~中旬にNK化成肥料を1平方メートル当たり30g施用します。
9.収穫
開花後35~40日が収穫の目安ですサヤが上向きから垂れ下がり、縫合線が色ずく頃でサヤを開くと胎座跡が黒変する前です。収穫適期のサヤは手で容易にもぎ取れますので、下節位から数回収穫します。
10.ソラマメの早出し栽培
ソラマメは一定の低温に合うと花芽が分化する特性があります。この特性を利用し、人工的に花芽を分化させることにより早出し栽培をすることができます。
表 作型と収穫期
11.種子の低温処理法
早出し栽培では、十分な花を分化させるために、種にあらかじめ低温処理をする必用があります。種は一昼夜流水につけ、吸水させて催芽をさせます。
浸積が終わると、日陰か恒温室で催芽させます。そのときの温度は20℃前後にします。催芽床は6cm程度の深さのトロ箱か育苗箱にバーミキュライトを入れて、4~5cm間隔に種をまきます。そしてその上にバーミキュライトで種がわずかに見える程度に覆土し、十分灌水した後催芽させます。4~5日後根長2~3cmに発根しますので、その状態のまま3℃で低温処理します。
低温処理中は催芽時と同様、乾燥防止につとめ、有孔ポリフィルムなどで被覆し、種に直接冷風を当てないようにします。特に乾燥する場合は、あらかじめ庫内で冷やした水を散布します。
低温処理期間は、最低20日間程度が必用ですが、種をまく時期が遅くなるほど、低温処理効果が少なくなります。低温処理効果は、1.開花が早くなる2.開花節位が下がる。3.草丈が低くなる4.分枝数が少なくなる等の利点があるが、催芽や低温処理技術がまずいと、種が腐ったりします。低温処理後は、3℃の庫内から外気の高温条件下に移すと発芽障害を起こしやすいので、1日程度は15~20℃の室で純化させてから、日中の高温時をさけて種をまきます。
ツイート
